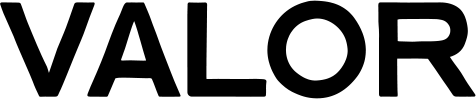モードジャズの原点!マイルス・デイビス『カインド・オブ・ブルー』

Aventure編集部


1959年8月にリリースされた、モード・ジャズの原点であるマイルス・デイビスのスタジオ・アルバム『カインド・オブ・ブルー』。従来のジャズの枠を飛び越えた本作は、マイルス・デイビスのリリシズムの頂点を極めた名盤でもあります。この記事では、マイルス・デイビスの紹介をはじめ、メンバーの変遷、『カインド・オブ・ブルー』の収録曲の聴きどころなどを解説します。
マイルス・デイビスの紹介
この投稿をInstagramで見る
名盤『カインド・オブ・ブルー』の魅力に迫る前に、マイルス・デイビスのプロフィールについて紹介します。バンドメンバー及びレコーディングメンバーの変遷、新しいジャズのスタイルの開拓についても紹介するので、見ていきましょう。
マイルス・デイビスのプロフィール
マイルス・デイビスは1926年にアメリカ合衆国イリノイ州オルトンにて生まれ、12歳でトランペットを始めます。高校在学中にはユニオン・カードを手に入れ、セントルイスのクラブに出演するようになり、才能を開花させました。
高校卒業後、当時の人気バンド「ビリー・エクスタイン楽団」がセントルイスを訪れた際、マイルス・デイビスは病気で休んでいたトランペット奏者の代役として急遽演奏に参加しました。
マイルス・デイビスが演奏に参加したころ、ビリー・エクスタイン楽団にはアルトサックス奏者のチャーリー・パーカーとトランペット奏者のディジー・ガレスピーが所属していました。2人は第一線で活躍する売れっ子ミュージシャンであり、彼は若くして憧れのミュージシャンたちとの共演を果たしたのです。
その後、マイルス・デイビスは彼らと演奏したときの感動を忘れられず、彼らを追ってニューヨークに移り住みます。
バンドメンバー及びレコーディングメンバーの変遷
マイルス・デイビス率いるバンドメンバー及びレコーディングメンバーの変遷について、第一期クインテット、第二期クインテットに焦点を当てて解説します。
第一期クインテット
1955年、ジョン・コルトレーン(ts)、レッド・ガーランド(p)、ポール・チェンバース(b)、フィリー・ジョー・ジョーンズ(ds)を含む5人編成のバンドが結成されました。同バンドは、後に第一期クインテットと呼ばれます。
結成から間もなくしてコロムビア・レコードと契約した彼らは、1956年には代表作の一つである『ラウンド・アバウト・ミッドナイト』をリリースします。
結成から3年後、マイルス・デイビスはアルトサックス奏者のキャノンボール・アダレイをメンバーに加えて、バンドメンバーを6人編成に変更しました。その後、ピアノ奏者のレッド・ガーランドが脱退し、ビル・エバンスが加入します。しかし、ビル・エバンスはわずか7ヶ月で脱退し、代わりにウィントン・ケリーが加入しました。
こうしたメンバーの変遷を経て、1959年にジャズの名盤『カインド・オブ・ブルー』の制作に取り掛かっていきます。
第二期クインテット
1964年に結成された5人編成のバンドは、第二期クインテットと呼ばれています。第二期クインテットは、高い実力を誇る若手プレイヤーのウェイン・ショーター(ts)、ハービー・ハンコック(p)、ロン・カーター(b)、トニー・ウィリアムス(ds)を含む5人編成です。彼らは後にジャズ界に大きな影響を与える存在へと成長していきます。
第二期クインテットでは、アルバム『E.S.P.』『マイルス・スマイルズ』『ソーサラー』『ネフェルティティ』などをリリースしました。
1960年代後半から70年代前半にかけては、ピアノ奏者のチック・コリアやキース・ジャレットを起用します。80年代には、ベーシストのマーカス・ミラーや、ギタリストのマイク・スターンなどが抜擢されます。
新しいジャズのスタイル「モード・ジャズ」を開拓
1940年から50年にかけての主流である「ビ・バップ」は、少人数編成でコード進行をもとに即興演奏するジャズ・スタイルです。当時のミュージシャンは、ビ・バップのコード進行に基づき、できるだけ速く多くの音符を演奏し、楽曲を表現していました。
しかし、最新鋭のサウンドを追求するマイルス・デイビスにとって、ビ・バップのスタイルは終着点ではありませんでした。マイルス・デイビスはビ・バップの複雑なコード進行に囚われず、よりシンプルなコード進行を用い、モードと呼ばれる音階を使ってアドリブを展開してフレーズを作るスタイルを生み出しました。このモード・ジャズにより自由度が増し、メロディ・ラインの選択肢も増えたと言われています。
マイルス・デイビスの名盤『カインド・オブ・ブルー』
この投稿をInstagramで見る
ここからは、マイルス・デイビスのスタジオ・アルバム『カインド・オブ・ブルー』に迫っていきましょう。名盤『カインド・オブ・ブルー』の制作背景と作風について紹介します。
『カインド・オブ・ブルー』の制作背景
スタジオ・アルバム『カインド・オブ・ブルー』の制作は、1959年3月2日と4月22日の2日間で行われました。わずか2日間で、マイルス・デイビスはメンバーへの指示からレコーディングまで独力で統率しました。
参加メンバーはジョン・コルトレーン(ts)、キャノンボール・アダレイ(as)、ポール・チェンバース(bs)、ジミー・コブ(ds)、ウィントン・ケリー(p)。そして、ビル・エバンス(p)もピアノ奏者として参加しています。
ビル・エバンスは、4ヶ月前に既に脱退していましたが、マイルス・デイビスは同作品録音のために、モード手法に造詣のあるビル・エバンスに声をかけたのです。
2日間の録音期間を経て、1959年8月にスタジオ・アルバム『カインド・オブ・ブルー』をリリースしました。同作品は世界で累計1,000万枚以上のセールスを成し遂げたのです。この作品のリリースを境に当時のジャズシーンでは、モード・ジャズを演奏するアーティストが続々と登場しました。
『カインド・オブ・ブルー』の作風
スタジオ・アルバム『カインド・オブ・ブルー』は、モード・ジャズを生み出したきっかけとなった名盤です。
同作品は多重録音や大規模なオーケストラ、それまでのメインストリームであるビ・バップのような複雑なコード進行も用いずに無駄な部分をそぎ落としています。メロディラインはいたってシンプルであるのに、美しいハーモニーがあるのがモード・ジャズの特色です。
『カインド・オブ・ブルー』収録曲の聴きどころ
この投稿をInstagramで見る
マイルス・デイビスの名盤『カインド・オブ・ブルー』の収録曲の中から、3曲をピックアップして楽曲の特徴を紹介します。
『ソー・ホワット』
アルバム1曲目の収録曲『ソー・ホワット』は、ピアノとベースの静寂感のあるイントロから始まります。イントロに続き、マイルス・デイビスのソロからジョン・コルトレーンのサックス、ビル・エバンスのピアノ演奏とバトンが繋がれていきます。
緊張感の中で繰り広げられる各パートの抑揚を抑えた情熱のある演奏は、鳥肌モノ。まさにモード・ジャズを象徴するような、即興演奏が生むスタイリッシュでクールな楽曲です。タイトル『ソー・ホワット』はマイルス・デイビスの口癖に由来しているそうです。
『フレディ・フリーローダー』
アルバム2曲目の収録曲『フレディ・フリーローダー』は、曲の構成やテンポが前曲と似ているため、『ソー・ホワット』の余韻に浸りながら聴き進められます。
しかし、似て非なるものでもあり、『フレディ・フリーローダー』は濃厚なブルース・フィーリングで、夜の雰囲気に満ち溢れた楽曲です。ビル・エバンスの軽やかで華やかなピアノの音色をベースにした、リズム&ブルースの世界に酔いしれてしまう人も少なくないでしょう。
『ブルー・イン・グリーン』
アルバム3曲目の収録曲『ブルー・イン・グリーン』は、ビル・エバンスとマイルス・デイビスの2人の音色が混じり合ったしっとりとしたジャズ・バラード。アルバム『カインド・オブ・ブルー』のハイライトとも言える楽曲です。
ビル・エバンスの物憂げなピアノの音色に、マイルスがミュートで鳴らす音色が重なり抒情的な美しさが表現されています。アルバム『カインド・オブ・ブルー』の中で、最も詩的で美しい楽曲だと言っても過言ではありません。
『カインド・オブ・ブルー』のジャケット
この投稿をInstagramで見る
ここでは、マイルス・デイビスの名盤『カインド・オブ・ブルー』のジャケットについて解説していきましょう。ジャケットの裏面にあるライナーノーツと裏話について紹介します。
ジャケットの裏面にあるライナーノーツ
この投稿をInstagramで見る
『カインド・オブ・ブルー』のジャケット裏面には、ピアニストとして参加しているビル・エバンスが執筆したライナーノーツが記載されています。
その中では、日本古来の水墨画を例にしてバンドが取り組んだモード・ジャズの即興演奏について解説しています。
曲順の表記が誤っていた?
この投稿をInstagramで見る
アルバム『カインド・オブ・ブルー』の発売当初、ジャケット裏面に記載された『オール・ブルース』と『フラメンコ・スケッチズ』の2曲の曲順が入れ違って表記されていました。この曲順表記のミスは1990年代頃まで続き、多くのリスナーの混乱を招いたと言われています。
従来のジャズの常識を覆した名盤『カインド・オブ・ブルー』
マイルス・デイビスの『カインド・オブ・ブルー』は、モード・ジャズの原点であるスタジオ・アルバムです。ジャズ界最大のヒット作であり、今もなお多くのジャズファンに愛されています。
後世のアーティストにも大きな影響を与えた名盤ですので、ジャズファンのみならず音楽ファンなら一聴すべき作品です。一音一音を噛みしめて聴くのに相応しい一枚ですので、この機会にぜひお楽しみください。